| 弾性波調査について (調査計画については、「沖縄防衛施設庁が出した現地技術調査資料」をごらんくだ さい。) 現地技術調査では、海底の地質構造を調べるために「弾性波調査」が行われるとのこ とですが、この弾性波調査とはいったいどのようなものなのでしょうか? 当会は、防衛施設庁の説明を受けたとき、この件について質問をしましたが、「音波 で地質を調べるものである。」としか回答は得られず、これ以上のものは引き出せま せんでした。 そこで、一般に行われている弾性波調査の内容をここにご紹介します。 海底の地質構造を調べるためには「反射法地震探査」が特に有効とされています。こ こでいう「弾性波調査」とはこれを指していると考えられます。または、簡単に「音 波探査」と呼ばれているものも、これにあたるでしょう。この方法は、弾性波が伝播 速度の異なる物質が接する境界面で反射する性質を利用して、発震された弾性波の反 射波を観測することによって地下の地質構造を知るというものです。海域における反 射法地震探査では、調査船を一定速度で航行させながら弾性波を一定距離間隔で発震 させ、海底下の反射記録を連続的に取得します。このデータを処理すると、海底地下 の地質構造の断面図が得られ、その断面図から地質の構造形態、不整合面、堆積の微 細構造までがわかるとのことです。ただし、得られる記録の分解能や深度、SN比は、 どのような震源を選択するかに大きく影響されます。浅海域では、主にエアガン、ウ ォーターガン、スパーカーが震源として用いられ、一般的には、エアガンは発震出力 が大きく低周波数、ウォーターガンは中程度の発震出力でやや高周波数、スパーカー は発震出力が小さく最も高周波数の震源となります。弾性波は、周波数が低いほど地 下深部まで届きますが分解能は悪くなり、逆に周波数が高いと分解能はよくなります が深部まで届きません。したがって、どのくらいの深さの構造が知りたいか、どの程 度の分解能が必要かによって、選択する震源は異なってくるわけです。一般に、周波 数10kHz以上の弾性波は海底地形調査に、数kHzの弾性波は海底下数十mの未固結堆積 物探査に用い、数十Hz以下の弾性波は海底下数km以上の深さの地層・構造探査に使わ れます。 以上から推定すると、辺野古で行われようとしている弾性波調査には、周波数が数kHzのものが使われると考えられます。当会の会員の方が、海外の研究者に問い合わせ てくださったところによると、ジュゴンは周波数20kHz以下の音に対して感度を持ち、 最大感度は10kHz以下であるとのことです。つまり、ジュゴンが最も敏感な周波数帯 が、まさに弾性波調査に使われるものに一致することになります。これが、延長12km にもわたる測線上で発震されつづけるのです。当然、ジュゴンの行動に影響すること が考えられますし、距離によっては体に害を及ぼしかねません。 〔引用資料〕 http://criepi.denken.or.jp/jpn/PR/Review/No42/chap-2.pdf http://unit.aist.go.jp/mre/mre-mgl/survey_method/seismic.html 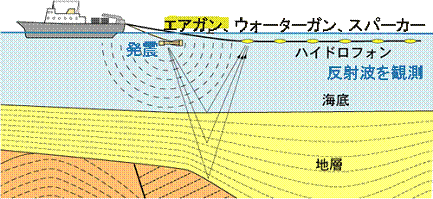 |